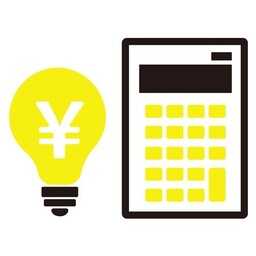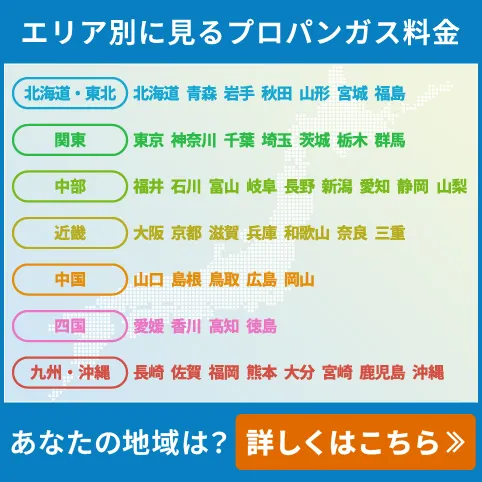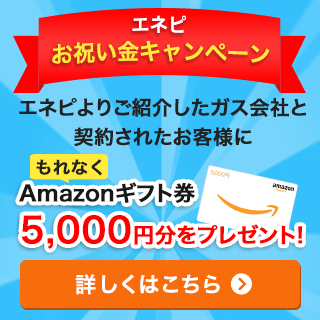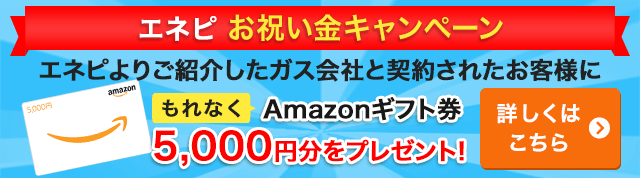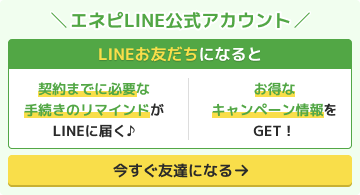電力自由化の仕組みと目的とは?
2016年、ついに電力小売の自由化がスタートします。ところで、電力自由化とはどういうことなのでしょうか?電力小売自由化の経緯や概要、目的について、分かりやすくお伝えします。
実は、電力の自由化の歴史は、既に2000年よりスタートしています。1990年代の円高や世界的な規制緩和の流れを受けて、世界的にみて高水準だった日本の電力の供給価格について、世界的に遜色のないコスト水準にすることを目指して、経済産業省の主導で、様々な制度改革が計画されてきました。その改革の本丸が、電力の自由化、つまり電力会社の選択肢を増やし、企業や個人など電力の需要家が自由に選べるようにすることだったのです。
これまで東京電力や関西電力など既存の電力会社が独占的に供給してきた電力でしたが、規制緩和によって民間企業など新たな電力供給の担い手の参入を促し、消費者にとって電力の購入先の選択肢を増やすことで、電力会社間での競争を生み、電力の安定供給や、電気料金の低下を目的としています。
ただし、一気に電力の全面自由化を行ってしまうと混乱が生じかねないため、段階的に自由化の対象を拡大していくことにしたのです(下図参照)。
電力自由化の経緯・目的

上記の図の通り、電力市場の自由化は、大きく4つの段階に分かれています。
① 2000年 大規模需要家(大規模工場やホテル、オフィスビルといった大口の電力需要家)
② 2004年 中規模需要家(契約電力500kW以上の、比較的大口の需要家)
③ 2005年 中規模需要家(50KW以上=高圧)
④ 2016年 小規模需要家(住宅家庭、事業所、コンビニ等、残りすべての需要家=低圧)
2015年の時点で、既に6割の電力需要家に対して、電力小売の自由化は進んでいたのですね。そして、2016年4月をもって、電力小売の全面自由化がスタートすることになります。家庭用を中心としたこの部門には、全国で約8,400万の利用者がいると言われており、今回の電力の小売自由化によって市場規模は7.5兆円に拡大すると見込まれています。この中には、電力システム改革に伴い、小売り自由化範囲の拡大や卸電力取引所(JEPX)、または電力広域的運営推進機関との新たな取引に対応するためのシステム開発・運用に係る金額も含まれています。
電力自由化の仕組み、新電力とは?
上記の電力自由化の経緯のとおり、電力市場の自由化によって、独占的に電力を供給していた従来の電力会社(東電、関電といった一般電気事業者)以外にも、新たな事業者が電力の需要家に対して電力を供給することができるようになりました。この新たに電力の小売に参入した事業者を、新電力(正式名称:特定規模電気事業者)と言います。当初は、英語表記でPPS(Power Producer and Supplier)と名付けられていましたが、用語がやや分かりづらいこともあり、2012年より新電力という名称に統一されています。
なお、似た用語として、特定電気事業者という名称がありますが、こちらは、再開発地域な限定された区域に対し、自前の発電設備や配線網を用いて電力供給を行う事業者のことを指しており、全く別の事業者となります。具体的には、六本木ヒルズに電力を供給する六本木エネルギーサービス株式会社や、JR目黒駅前ビルに電力供給を行う東日本旅客鉄道(JR東日本)株式会社など、5社が該当します(2015年6月時点)。
新電力は、1999年の電気事業法(電力事業が適切に運営され、電気需要家の利益が保護されるため、事業者が守るべきルールを定めた法律)の改正により、大口需要家への電力供給を行うことが出来るようになりました。あわせて、一般電気事業者が独占的に使用していた送電線も解放され、託送(たくそう)料金を支払うことで、需要家に電気を送り届けることができるようになりました。託送料金とは、送配電事業者が所有する送配電網を利用して需要家に電力を供給する際に支払う料金のことを言います。なお、2015年時点では送配電事業は一般電気事業者が兼ねているため、一般電気事業者への支払いとなります。
新電力の登録者数と電力供給実施事業者数
新電力の登録数は、2015年6月22日時点で、673社になります。ここ2年間での登録数が、6倍近くに急増していることになります。また、帝国データバンクの調査によれば、登録した企業の業種について、「卸売業」がトップの21.3%(構成比)、次いで「建設業」が14.8%、続いて「小売業」が13.0%となっています。こういった新電力の増加の背景の1つは、2016年の電力自由化に伴う電気と自社サービスのセット売りを通じた、自社の既存顧客のリテンション(維持)施策のためだと言えます。
そのため、BtoC(一般消費者向け)サービスを展開していて、多くの消費者を顧客として抱えている企業(たとえば、住宅メーカー、通信事業者、ガスなどのインフラ事業者、その他小売事業者等)にとっては、新電力に登録し、自社サービスと合わせて生活に欠かせないインフラである電気を自社顧客に提供することで、自社サービスのロイヤリティを高めようと画策しているのです。知名度の高い企業で、新電力に登録済みの企業の例としては、丸紅株式会社、パナソニック株式会社、昭和シェル株式会社、オリックス株式会社、シャープ株式会社等があります。詳細は、こちらの記事(「新電力会社の比較情報」)をご覧ください。
どうやって新電力になるか?
電力をどこから買うか選べるようになります!
電力自由化によって、まるでSFのような未来が訪れる!?
たとえば、スマートフォンなどと連動してホームエンターテイメント(娯楽)、ホームケア(高齢者や子供の見守り、高齢者介護など)といった他のサービスも提供されることになるでしょう。また、家庭内の電力を監視するスマートメーターの一種であるHEMS(Home Energy Management Service)が家電と連動することで、電気の「見える化」が可能となり、どの家電がどれくらいの電力を消費しているのかが一目瞭然となります。さらには、電力のカラーリング(電源が再生可能エネルギーなのか、化石燃料なのか、原子力なのか)により、より自分の趣向にあったエネルギーを選択して、使うことができるようになります。
最後に、自宅の電気代が高いとお困りの方に朗報です。
enepi(エネピ)が提供する『電気料金比較サービス』が、あなたの使い方に合わせた最適なプランをご提案し、自宅の電気代節約を実現します。
ちなみに、当サービスは平均月間1,500円の電気代削減という確かな実績に裏打ちされています。ぜひあなたも試してみてください。