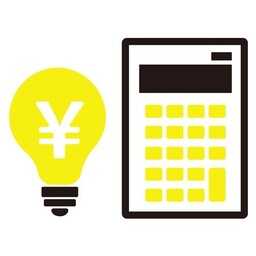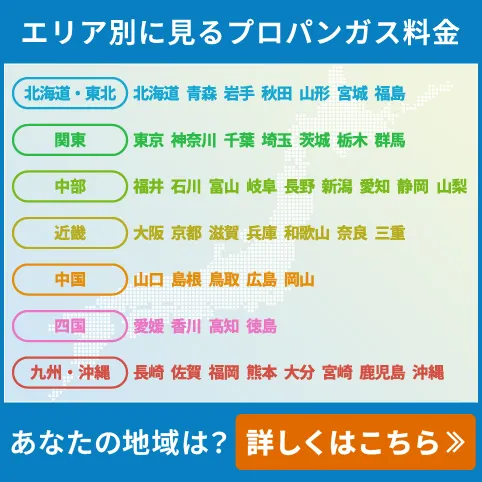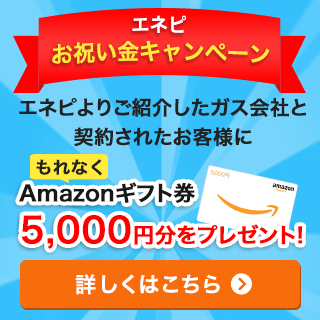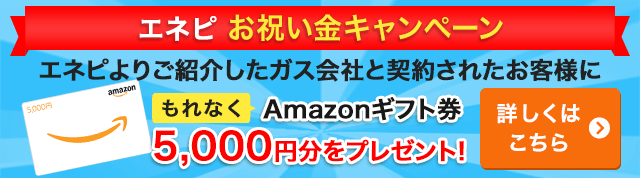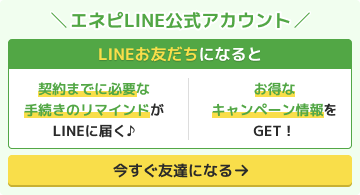2016年の電力の小売全面自由化を目前に控え、今後知名度が急に伸びると予想される言葉がスマートメーターです。
それと似た言葉で使用されることが多いHEMSがありますが、スマートメーターそしてHEMSとの違いについてご紹介します。スマートメーターとは

一方で、スマートメーターを使用すれば、電力量計から通信で電力会社にデータを転送するため、人力による計測作業が不要になります。
スマートメーターによって変わることは、電力検診のための人件費が削減が出来ることだけではありません。
スマートメーターを介して家庭内ネットワークを利用することで、リアムタイムに電力使用量を確認できる、いわゆる「電気の見える化」が実現できるのです。
「電気の見える化」によって電気の無駄遣いを削減できるため、家庭の電気代の節約ができる上に、環境保護にも貢献できます。
スマートメーターのメリット
スマートメーターを導入することによって、家庭内でどのくらい電力を消費したのかというデータを、常に確認できるようになります。
省エネに努めたくても、目標をどのように設定したら良いかわからなかったという方は、これまで多かったことでしょう。
しかし、はっきりとした数字が見えることによって、正確な目標設定ができるので、明確な節電対策が可能になります。
日ごと、時間ごとの電気使用実績を知ることができるので、家族のライフスタイルに合った電気料金プランのシミュレーションにも役立ちます。
また、夏の暑さや冬場の寒さの影響を受けて、強制的な節電が必要になるほど電力供給が逼迫した場合にも、スマートメーターは活躍します。
電力会社側が一時的に、地域単位や建物単位で、電力供給をコントロールすることができるのです。
スマートメーターのデメリット
データにはさまざまな個人情報を含んでいることもあるので、ウイルスやハッキングなどによる情報漏れを防ぐための万全なセキュリティ対策が必要です。
経済産業省内では「スマートメーター制度検討会」を設置し、有識者による会合を重ねています。
スマートメーターとHEMSの違い
HEMSとは「Home Energy Management System(ホーム・エネルギー・マネジメント・システム)」の略。
スマートメーターは通信機能を持った次世代型の電力量計のことを指すのに対し、「HEMS」は家庭内における電力を節約・最適化する管理システムのことを言います。
スマートメーターとHEMSとは、似たような位置づけで表される事が多いですが、それぞれ重要な役割分担があります。
スマートメーターで最も重要なものが、各家庭・地域の電力使用量を「外部に伝える」ことです。
外部とは主に電力会社であり、電力会社を通じていろいろなサービス提供を提供している第三者企業へも伝えることができます。
スマートメーターを導入することによるメリットは、私たちのような一般消費者より、電力会社の方が大きいのも特徴です。
電力会社側には人件費管理や、電力使用量をより正確に計測できるというメリットがあります。
電力の供給が安定すれば、もちろん消費者側もさらに電気を使いやすくなります。
一方、HEMSの役割は「エネルギーの見える化」、そして「機器の制御・管理」です。
住宅内の機器や設備をHEMSで繋ぐことによって、「どこの部屋で、どの機器が、どれ位の電力を消費したか」という内容を詳しく把握できます。
太陽光発電システムを導入している住宅なら、発電量まで確認できるのも嬉しい機能の一つ。
スマートメーターに比べて、HEMSの方が私たち消費者のメリットが大きいです。
節電・省エネに積極的に取り組めるだけではなく、スマートフォンなどで外部から住宅内の家電操作が可能なため、便利さな暮らしが手に入ります。
スマートメーターとHEMSがそれぞれの役割を果たすことで、通信・制御機能を備えた電力網が完成します。
スマートメーターとHEMSを連携すれば、さらに省エネに有効な施策を考えるヒントも得られるようになります。
スマートメーターの今後
さらに言うと、家庭だけではなくオフィスや店舗・工場など、あらゆる電力需要家に対してスマートメーターを導入させたいと考えられています。
スマートメーターの導入目標は、2014年4月に国が決定した「エネルギー基本計画」で掲げられた政策内容の一つなのです。
今後の導入計画
従来の電力メーターが設置されている台数は、国内全体で7,800万台ほどあります。
2020年代までにこの7,800万台をすべて切り替えたいというわけですが、現時点で国内の導入されたスマートメーターの総量は、まだ330万台程度です。
普及状況を考えると、東京電力の場合は5年以上にわたって年間300万台以上のスマートメーターを導入し続けなければならないため、毎年300億円規模の費用が発生する計算になります。
電力会社にとっては多額の負担になってしまいます。政府からの補助金制度も見込まれてはいますが、電力自由化などにより経営がさらに厳しくなっている昨今、大々的にスマートメーターを展開していくことは容易ではありません。
電力会社側の負担が増大すれば、やがては私たちが支払う電気代にも反映されてしまうでしょう。
スマートメーターは、エネルギー基本計画を始めた当初、一部試験的に東京電力や関西電力などで導入されていました。
しかし、できる限り早急に計画を達成するために、今では北海道電力や九州電力などといった国内の電力会社10社で本格的に導入され出しています。
また仕様に関しては、企業や家庭などの機器・システムと、スマートメーターを連携するための通信システムが心配されています。
スマートメーターや通信のためのシステムは、いずれも多様なメーカーから開発・販売されていきます。
メーカーや機種によって、連携させた通信システムとの相性が合わなかった場合、電気機器とHEMSを接続する際に制約が出てしまう可能性が考えられます。
制約を解消するために、さらなるコストがかさんでしまうトラブルも予想されるため、まだまだスマートメーターはメリットばかりとは言えないのが現状のようです。
スマートメーターによって変わる生活
家庭内で「電気が見える化」することにより、はっきりとした節電・省エネ計画を立てられるようになります。
データを確認した電力会社からは、生活時間に見合った料金プランが提案されるので、光熱費の管理が容易になることは間違いありません。
さらに将来的には、遠く離れた家に住む高齢者の見守り機能や、福祉・介護支援機能などのサービスも期待されています。
スマートメーターから送られてくる電気の使用状況に異変が見られた場合、電力会社から地域の医療・介護センターに対応依頼をすることができるのです。
まとめ
最後に、自宅の電気代が高いとお困りの方に朗報です。
enepi(エネピ)が提供する『電気料金比較サービス』が、あなたの使い方に合わせた最適なプランをご提案し、自宅の電気代節約を実現します。
ちなみに、当サービスは平均月間1,500円の電気代削減という確かな実績に裏打ちされています。ぜひあなたも試してみてください。