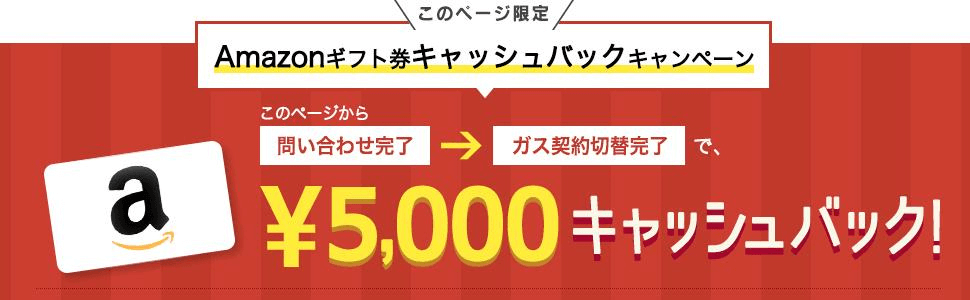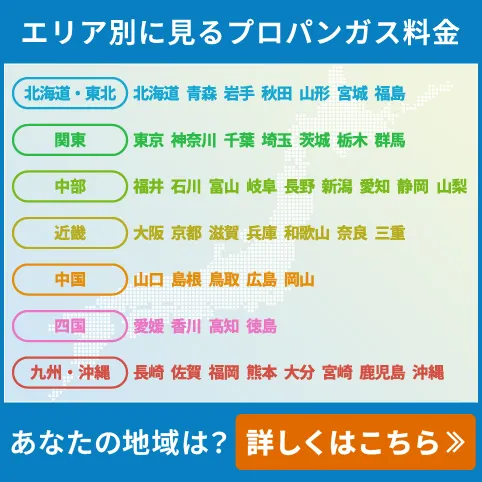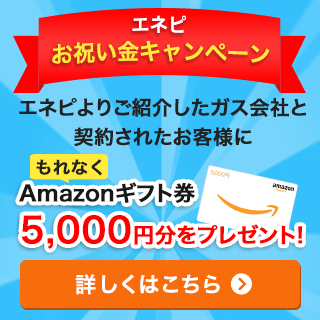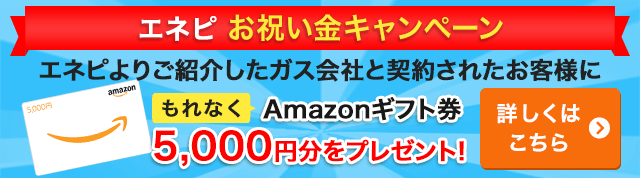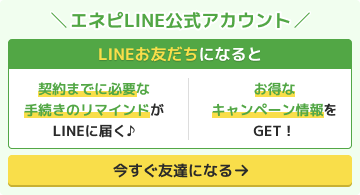ガス自由化とは?
ガス自由化の仕組み
ガス自由化のメリット
電力自由化とは?
電力自由化の仕組み
2016年4月にスタートした電力自由化ですが、
実はそれ以前から、大契約電力(50kW)までの需要家に対してはすでに電力は自由化されていました。
では、今回の電力自由化とは何を意味するのでしょうか。
2016年4月以降は、これまで自由化の対象外であった50kW未満の需要家、具体的には一般家庭やコンビニエンスストア、小規模の工場などに対して、電力の小売りが自由化されたのです。
これまで、50kW未満の需要家に対する電力は、国が定める一般電気事業者が独占的に提供してきましたが、消費者が自由に電力会社を選ぶことができるようになったのです。電力自由化のメリット
【徹底比較】ガス自由化と電力自由化
電力自由化とガス自由化の類似点
自由化以前は、地域で定められた業者の電気・ガス会社としか契約することができなかったため、
このため、価格競争が起こらず、電気代・ガス代の値下げがほとんどされないという問題点がありました。
それぞれの自由化によって、消費者は電気・ガスの供給を受ける業者を自由に選択できるようになりました。
安い料金プランや、会社独自のサービス内容など、ライフスタイルに合わせてユーザーが決められるというわけです。
顧客を獲得したい事業者たちが価格競争を行うことにより、電気・ガスが消費者に低価格で提供されていくことが期待できます。
ただし契約先を自分で選ぶ上で、契約内容が本当に最良のものであるか吟味する必要もあります。
電力自由化とガス自由化の違いは?
具体的にどれほどの差異があるのでしょうか。
<違い①>市場規模の大きさ

<違い②>新規参入の難しさ

新規参入のハードル1
ガス自由化の場合は
自社でLNG(液化天然ガス)輸入基地を
保有していなければ、
市場参入することができません。
LNG輸入基地もしくは
同等の設備を持っているのは、
ガス会社と電力会社、
石油会社くらいのものです。
現状ではこれは極めて高い
参入障壁になっており、
ガス事業への新規参入が困難だと
されている最大の理由の一つと言えます。
新規参入のハードル2
ガス管などの託送供給設備の
課題もあります。
前述の通り、ガスを各家庭店舗などへ
届けるにはガス導管・パイプラインが必要です。
東京ガス・大阪ガス・東邦ガスの
大手3社については、
ガス導管を敷設・管理する事業を、
2022年4月までにガス製造や
小売事業と分離・別会社化することが
義務づけられています。
もし複数の業者が同じエリア内に
ガス導管を敷設してしまうと、
導管が二重になって非効率になるので、
ガス導管はこれまでと同様に
地域独占を継続します。
新規参入事業者は、ガス導管の
利用料(託送料)を支払えば
ガス供給は可能ですが、借りられる
ガス導管がない場合は新設しなくてはなりません。
ところがガス導管の設置には
莫大な費用がかかります。
市場規模が決して大きくはないため、
回収できるかわからない建設費を
投資する会社が増えるとは考えにくいのです。
ガス自由化参入企業


まとめ
しかしながら、ガス自由化については対象となる消費者数が少なく、
今後、電力自由化・ガス自由化によって全国の人の暮らしが豊かになっていくことを期待したいですね。
最後に、自宅の電気代が高いとお困りの方に朗報です。
enepi(エネピ)が提供する『電気料金比較サービス』が、あなたの使い方に合わせた最適なプランをご提案し、自宅の電気代節約を実現します。
ちなみに、当サービスは平均月間1,500円の電気代削減という確かな実績に裏打ちされています。ぜひあなたも試してみてください。